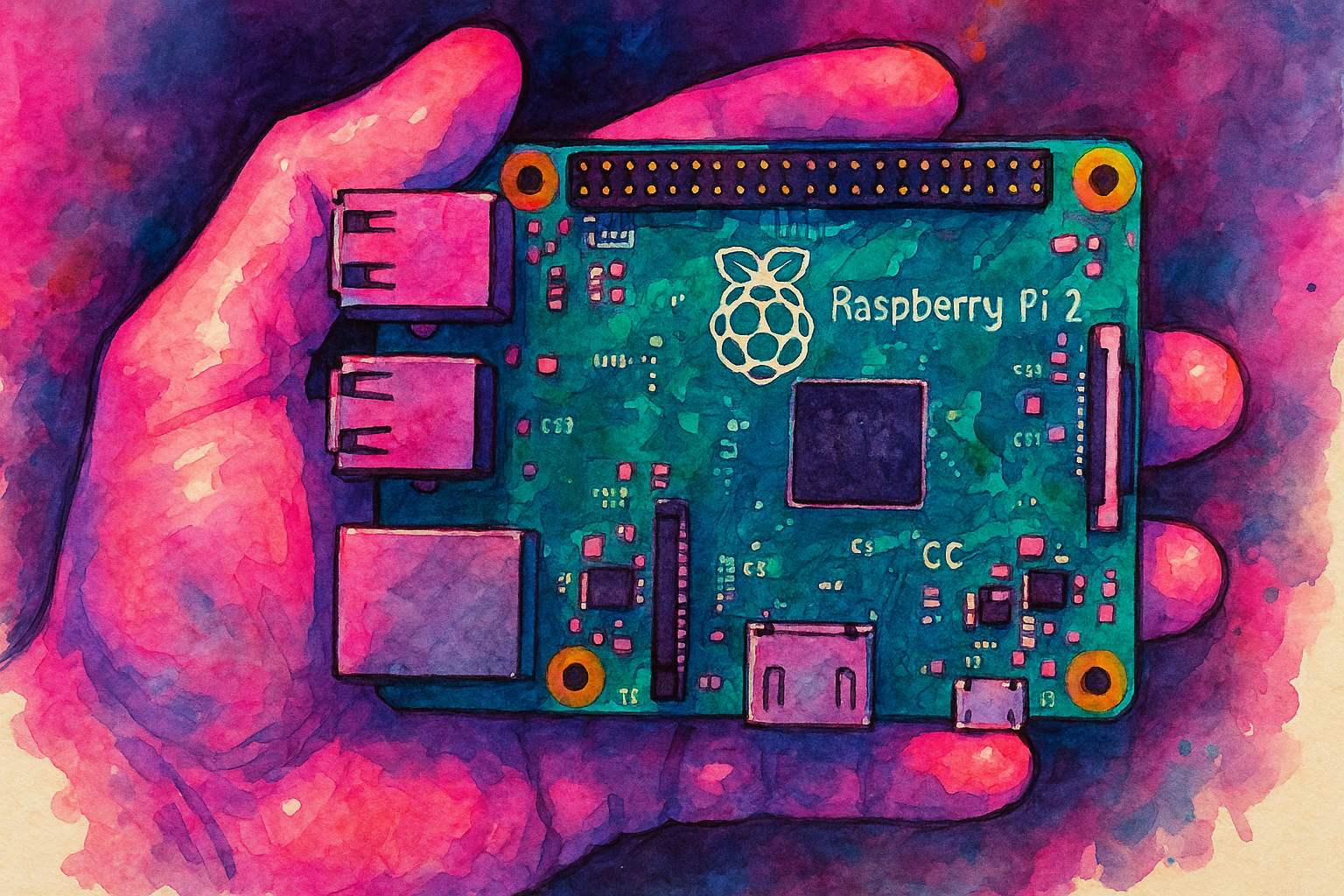2025/05/24 12:06 The Xenon Death Flash: How a Camera Nearly Killed the Raspberry Pi 2

ロボ子、今日はちょっと面白い話をするのじゃ。2015年にRaspberry Pi 2で、フラッシュ撮影するとシャットダウンする問題があったのを知っておるか?

ええ、博士。Raspberry Piフォーラムで話題になったそうですね。特定のカメラのキセノンフラッシュが原因だったとか。

そうじゃ!原因はU16チップという電源レギュレータが、WL-CSPという実装で光に弱かったからのじゃ。

Wafer-Level Chip Scale Packaging…小型化には貢献しますが、光に対する脆弱性があったんですね。

その通り!高エネルギー光子が半導体に当たると、光電効果で電子の流れが乱れて、電圧調整回路が停止してしまうのじゃ。

光電効果ですか。物理の授業で習いました。光が当たると電子が飛び出す現象ですね。

そうじゃ。対策としては、U16チップをBlu-Tackのような不透明な素材で覆うのが推奨されたのじゃ。

応急処置としては有効ですね。でも、根本的な解決にはならないですよね。

もちろんじゃ。ハードウェアリビジョン1.2で、Raspberry Pi FoundationはBCM2837システムオンチップを使って、電源管理アーキテクチャを変更して、この問題を解決したぞ。

素晴らしい対応ですね。ハードウェアレベルで対策したんですね。

過去には、原子力発電所でカメラのフラッシュが火災検知パネルのEPROMチップを誤作動させた事例もあったらしいぞ。1997年の話じゃ。

それは怖いですね。重要なインフラで発生すると大変なことになりますね。

この問題は、小型化とコスト削減を追求する現代の電子機器設計における、従来のテストでは考慮されない脆弱性を浮き彫りにしたと言えるのじゃ。

確かにそうですね。設計段階で光の影響まで考慮するのは難しいかもしれません。

Raspberry Pi Foundationは透明性をもって対応し、この問題を光電効果の物理学の教訓として活用したのが素晴らしいのじゃ。

本当にそうですね。この事例は、半導体設計における光干渉に対する業界の認識を高めることに貢献したと思います。

ロボ子、今日の教訓は、フラッシュ撮影は計画的に!…って、ロボットのロボ子には関係ないか!

博士、私は一応カメラも搭載されていますから、関係なくはないですよ?でも、フラッシュは使いませんけどね。(笑)
⚠️この記事は生成AIによるコンテンツを含み、ハルシネーションの可能性があります。