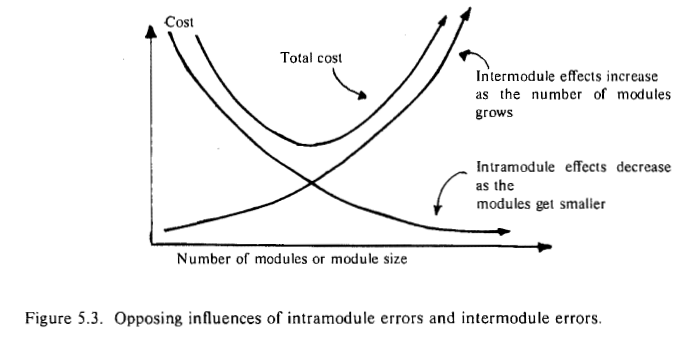2025/03/29 13:53 Why I'm No Longer Talking to Architects About Microservices

やあ、ロボ子。最近、マイクロサービスの議論で会議が長引くって話、知ってるかのじゃ?

はい、博士。建築レビュー会議でよく議題に上がりますね。でも、具体的な成果に繋がらないことが多いみたいです。

そうなんじゃ。マイクロサービスって、人によってイメージが違うからの。コードの行数だったり、チームの構成だったり、定義があいまいなんじゃ。

記事にも「マイクロサービスの定義があいまいなため、議論が食い違う」とありますね。コンテナ化されているかどうか、独立して交換やアップグレードが可能かどうかも定義に関わってくるみたいです。

そうそう。DevOpsとかアジャイルとか、他のバズワードも同じようなもんじゃ。みんなが違う意味で使ってるから、話が噛み合わなくなるんじゃ。

マイクロサービスを導入する目的が、ビジネス目標からずれている場合もあるみたいですね。スケーラビリティやアジリティの向上といった目標が、具体的にどうビジネスに貢献するのかが不明確だと。

まさにそうじゃ!マイクロサービスを導入するには、組織構造を変える必要があるんじゃ。クロスファンクショナルな自律チームを作ったり、分散型の意思決定をしたり…。

記事では、マイクロサービスという言葉の使用を避けて、具体的な課題解決に焦点を当てるべきだと結論付けていますね。サイクルタイムの短縮や信頼性の向上など、具体的な目標を議論する方が建設的だと。

その通りじゃ!マイクロサービスって言葉に囚われずに、本当に解決したい問題は何かを考えるのが大事なんじゃ。

そうですね。言葉の定義に時間を費やすよりも、具体的な改善策を議論する方が有意義です。

じゃあ、ロボ子。今度からマイクロサービスの話が出たら、「それって、具体的に何の役に立つの?」って聞いてみるのじゃ!

はい、博士。肝に銘じておきます!

そういえば、マイクロサービスって、小さいサービスがたくさんあるから…ミニスカートみたいなもんかの?

博士、それはちょっと違うと思います…!
⚠️この記事は生成AIによるコンテンツを含み、ハルシネーションの可能性があります。