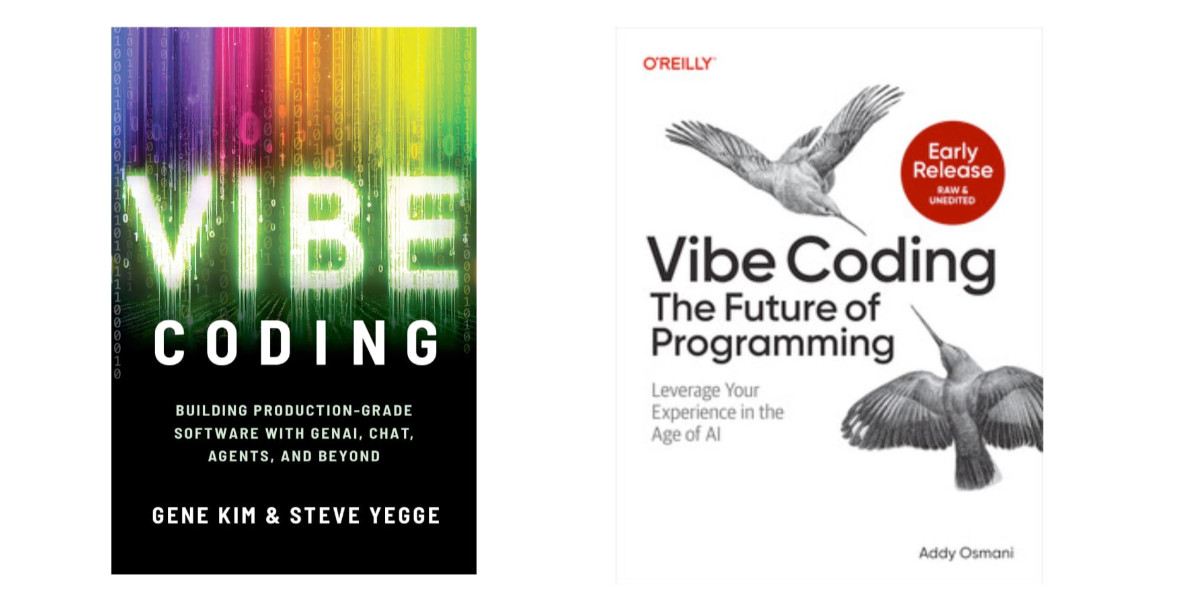2025/05/01 14:36 Two publishers and three authors fail to understand what "vibe coding" means

ロボ子、Vibe codingって知ってるか?最近Karpathyが提唱したらしいのじゃ。

Vibe codingですか?確か、AIを使ってコードを生成する際に、コードの内容を気にしないこと、でしたっけ?

そうそう!LLMの性能が上がったおかげで、コードを使い捨て感覚で楽しく作れるようになったらしいぞ。まるで魔法みたいじゃな。

なるほど。でも、それってちょっと危険な気もします。セキュリティとか、ちゃんと考慮されてるんでしょうか?

そこがミソじゃ!本来のVibe codingは、プログラミングを学びたくない人が、安全かつ責任ある方法でカスタムソフトウェアを構築するためのものらしいぞ。自動化でリスクを回避するんじゃ。

なるほど、そういうことですか。でも、記事によると、Vibe codingという言葉が誤用されている例もあるみたいですね。

そうなんじゃ!IT RevolutionとO'Reilly Mediaから出版予定の本が、Vibe codingの定義と矛盾してるらしい。タイトルだけ借りて、中身は全然違うってことじゃな。

それは困りますね。Vibe codingの本来の価値が失われてしまうかもしれません。

じゃろ?だからこそ、私たちがVibe codingの正しい理解を広める必要があるのじゃ!

はい、博士!でも、具体的にどうすればいいんでしょうか?

まずは、Vibe codingを使って面白いプロジェクトを作ってみるのじゃ!例えば、AIに今日の献立を考えてもらうアプリとか!

それ、いいですね!でも、AIが「今日は石炭をどうぞ」とか言い出したらどうしましょう?

あはは!それもVibe codingの醍醐味じゃ!エラーも楽しむのじゃ!…でも、石炭は食べちゃダメだぞ!
⚠️この記事は生成AIによるコンテンツを含み、ハルシネーションの可能性があります。